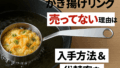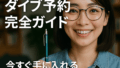あたためた料理を、もっとおいしく。
「せいろ どこで買える?」そんな疑問を持ったあなたに、この記事ではピッタリの答えをお届けします。
せいろは、実は100均・無印良品・ニトリから中華街の専門店、Amazonや楽天まで、購入できる場所は意外とたくさんあります。
でも「どこで買うべきか」「どんなサイズがいいか」「セットで揃えたほうがいいのか」…迷ってしまうのも事実。
この記事では、せいろの売ってる場所を徹底比較しながら、初心者でも失敗しない選び方・人気レシピ・便利な使い方までまるごと解説!
読めばあなたも、きっと「これが欲しかった!」という一台に出会えます。
この記事を参考に、あたたかくて優しい蒸し料理生活をはじめてみませんか?
・せいろはどこで買える?おすすめ購入先を徹底解説
・せいろを選ぶときに押さえたいポイントとは?
・せいろを使うならこれ!活用レシピと便利テクニック
せいろはどこで買える?おすすめ購入先を徹底解説

せいろはどこで買える?おすすめ購入先を徹底解説していきます。
100均で買えるせいろ:ダイソー・セリア・キャンドゥ
近年の100均は、調理道具もかなり充実していますよね。
実は、ダイソーやセリア、キャンドゥなどでは、コンパクトサイズの蒸し器や簡易せいろが販売されています。
特にダイソーでは、330円(税込)で買える「ステンレス製の折りたたみ蒸し器」が人気。
一方、竹製の本格的なせいろは少なく、どちらかといえば”お試し”感覚での購入が向いています。
「せいろに興味はあるけど、いきなり高いのはちょっと…」という人には、こういった100均アイテムから始めるのもアリ。
ただし、耐久性やサイズ展開に限りがあるので、長期使用や複数人分の料理には不向きかもしれません。
私も最初はダイソーで試しましたが、蒸し器の魅力を知るには十分なクオリティでしたよ〜!
無印良品やニトリなど生活雑貨店でも手に入る
少し本格的にせいろを探したい人には、無印良品やニトリがぴったり。
無印の竹せいろは、見た目もシンプルで美しく、価格も比較的お手頃。
例えば、21cmの2段タイプで3,000〜4,000円程度で販売されています。
また、ニトリでは鍋付きのセット販売もあり、すぐに使い始めたい人に便利な構成になっているのが嬉しいポイント。
ロフトやハンズなどでも取り扱いがあり、実物を手に取って選べる安心感があります。
「ネットで買うのはちょっと不安…」という人には、こうした生活雑貨店がおすすめです。
素材やサイズ感を実際に見てから購入できるのはやっぱり安心ですよね〜!
中華街や専門店で見つかる本格せいろ
「せっかくなら本格的なせいろが欲しい!」というこだわり派には、中華街や調理道具の専門店がおすすめ。
たとえば、横浜中華街の「照宝」はプロの料理人にも愛用されている有名店。
竹製・杉製のせいろをはじめ、鍋や専用シートなどの周辺グッズも一式揃います。
また、高知県の老舗「竹虎」など、地域に根ざした伝統工芸の技術が光るブランドもあります。
こういった専門店では、品質はもちろん、サイズ感や使い心地までスタッフに相談できるのも強みです。
長く愛用したい人やプレゼント用途には、こうした信頼のおける専門店での購入がベストですね。
私は照宝で見た職人の手仕事に一目惚れして、つい衝動買いしちゃいました…笑。
Amazon・楽天など通販での購入が一番手軽
やっぱり一番手軽なのは、ネット通販!
Amazon・楽天・Yahoo!ショッピングなどでは、せいろの取り扱いが非常に豊富です。
サイズ・素材・段数・セット内容など、細かい条件で検索できるので、自分にぴったりの1台が見つかりやすいのが特徴。
しかも、レビューで実際に使った人の感想が読めるのもありがたいポイント。
たとえば、21cmの2段セットに蒸し鍋やシートまでついたスターターキットは、3,000円前後で手に入ります。
ポイント還元やクーポンの対象になることもあるので、タイミングによってはかなりお得に買えちゃうかも!
私も楽天で購入しましたが、翌日には届いてすぐに蒸し料理を楽しめました〜!
せいろの価格帯と選び方のコツ
せいろの価格は、本当にピンキリです。
以下の表を参考にしてみてください。
| サイズ | 価格帯(目安) | 特徴 |
|---|---|---|
| 小型(〜18cm) | 1,000〜3,000円 | 1〜2人用。コンパクトで扱いやすい |
| 中型(21〜24cm) | 3,000〜6,000円 | 一般家庭向け。使いやすさと量のバランス◎ |
| 大型(27cm以上) | 6,000円〜10,000円以上 | 家族向け・大量調理向け。収納には注意 |
「とりあえず使ってみたい」なら、21cm前後の2段セットから始めるのが無難です。
サイズと段数に加えて、鍋との相性も要チェック。
あとは、竹や杉などの素材選びもポイントですね。
見た目や香り、耐久性などがそれぞれ違うので、自分の好みに合わせて選んでくださいね。
失敗しない!初心者向けせいろセットの選び方
せいろ初心者さんに一番おすすめなのが「スターターセット」。
具体的には、以下のようなセット内容が理想です。
- せいろ本体(2段)
- 蓋
- 蒸し板または鍋付き
- クッキングシート
この内容なら、届いたその日から蒸し料理が始められます。
レビュー評価が高く、初心者向けと明記されている商品を選ぶと安心ですよ。
逆に、せいろ単体だけを購入して「鍋に乗らない」「蒸し板がない」と困るケースも多いので注意。
初めてならセット品を選ぶことで、そういった“落とし穴”を回避できます!
私の初購入はセットタイプでしたが、本当にストレスフリーでよかったですよ〜!
ギフトやプレゼント用におすすめの店舗
せいろって、実は「おしゃれなギフト」としても人気があるんです。
料理好きな人、健康志向な人にはとっても喜ばれます。
特におすすめなのは、以下のようなショップやブランドです。
- 無印良品(ラッピング対応あり)
- KEYUCA(センスの良いセット多数)
- 高島屋や三越などの百貨店
- 楽天・Amazonのギフトセットカテゴリ
贈り物なら、見た目の高級感やラッピング対応、レビュー評価もチェック。
熨斗(のし)やメッセージカードに対応してくれるショップだと、より気持ちが伝わりますね。
私も一度、友人の引っ越し祝いにせいろセットを贈ったら、めちゃくちゃ感激されました!
せいろを選ぶときに押さえたいポイントとは?
せいろを選ぶときに押さえたいポイントとは?初心者の方でも迷わず選べるよう、詳しく解説します。
サイズと段数の選び方:何人用かで決まる
せいろを選ぶとき、まず考えるべきは「サイズ」と「段数」。
たとえば、一人暮らしでちょっとした蒸し野菜を楽しむなら15cm前後の小型サイズで十分。
家族用であれば、21〜24cmの中型サイズがおすすめです。
段数については、1段だけよりも2段構成の方が一度に多く蒸せて便利。
料理中に「もう一品追加で蒸したい」と思ったとき、2段ならスムーズなんですよね。
以下の表に、人数ごとの目安サイズをまとめてみました。
| 人数 | サイズ目安 | 段数の目安 |
|---|---|---|
| 1人〜2人 | 15cm〜18cm | 1段または2段 |
| 3人〜4人 | 21cm〜24cm | 2段 |
| 5人以上 | 27cm以上 | 2段以上がおすすめ |
迷ったら21cmの2段が万能です。私も最初はこれから始めました!
素材の違い(竹・杉・桜・アルミ)の特徴と選び方
せいろにはさまざまな素材があり、それぞれに特徴があります。
中でもよく使われているのは「竹」と「杉」。
竹製は軽くて扱いやすく、価格も比較的お手頃。
一方、杉製は木目が美しく、ほんのり香る木の香りが料理を引き立ててくれます。
さらに、アルミ製やステンレス製のせいろもありますが、これらは業務用向き。
家庭で使うなら、やはり木製が見た目にも雰囲気が出ますよ。
素材の違いを表にするとこんな感じです👇
| 素材 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 竹 | 軽い・安価・ナチュラルな見た目 | 初心者・日常使い |
| 杉 | 高級感・香りが良い | 見た目や香り重視の人 |
| 桜 | 丈夫・耐水性が高い | 長く使いたい人 |
| アルミ・ステンレス | 洗いやすい・耐久性抜群 | 業務用・時短重視派 |
私は竹の軽さが好きなので、日常使いにはもっぱら竹せいろ派です!
蒸し板・鍋セットなど必要な付属品は?
せいろ単体で買っても、実はそのままでは使えない場合もあるんです。
なぜなら、「蒸し板(蒸し台)」や「せいろに合った鍋」が必要だから。
蒸し板がないと、鍋の上にせいろを置くとき不安定になったり、湯気の通りが悪くなったりします。
また、サイズが合わないとせいろが鍋に沈んでしまう…なんてことも。
そこでおすすめなのが、最初から「鍋+蒸し板+せいろ」の3点がセットになっているタイプ。
届いたその日から安心して使えるので、初心者の方にはとくに人気です。
レビューでも「セットにしてよかった!」という声が多いですよ〜。
せいろを使うならこれも必要!あると便利なグッズ
せいろをもっと快適に使いたいなら、次のアイテムがあると便利です!
- クッキングシート(食材のこびりつき防止)
- 布巾やガーゼ(柔らかく蒸すときに)
- 専用の蒸し鍋(サイズピッタリで安定感◎)
- お手入れ用のブラシ(カビ防止にも役立つ)
特に、専用のクッキングシートは超便利!
蒸したあと、せいろの底がベタつかず、洗う手間もグッと減ります。
私は最初、普通のクッキングシートを使って破れちゃったので、専用タイプを後から買い直しました…。
やっぱり、道具はちゃんと揃えると快適さが全然違いますよ〜!
安すぎるせいろに注意!よくある失敗例
せいろを選ぶときに「価格重視」で選んでしまうと、後悔するケースもあります。
たとえば、1,000円以下の激安せいろを買ってみたところ…
- 木がペラペラですぐ歪む
- 蓋がピッタリ閉まらない
- 木の匂いがきつすぎて食材に移る
なんてトラブルが実際に報告されています。
私も実は経験者なんですが、安物買いの後悔ってじわじわ来るんですよね…。
なので、レビューをちゃんと読む、信頼できるメーカーを選ぶ、セット内容を確認するなど、ひと手間を惜しまないことが大事。
「安い=得」ではなく、「安い=それなり」だと心得ておきましょう!
おすすめブランド・人気のレビュー商品まとめ
せいろ選びに迷ったら、人気ブランドやレビュー高評価商品を参考にするのが近道。
たとえば…
- 【吉冨士工芸】竹せいろ2段セット:Amazonレビュー星4.5以上
- 【Cranely】楽天市場で2600件以上のレビューあり
- 【KEYUCA】おしゃれな竹せいろ+鍋セットが人気
- 【照宝(横浜中華街)】本格志向の方にぴったり
これらのブランドは、品質・価格・使い勝手のバランスが良く、初心者からベテランまで幅広く支持されています。
レビュー数や評価は、そのまま信頼のバロメーターになるので、購入前に必ずチェックしましょう!
私もレビューを何十件も読み込んで、ようやく「これだ!」と思えるせいろに出会えましたよ😊
使い勝手や耐久性で選ぶならここに注目
せいろは一度買えば、数年〜10年以上使えるアイテム。
だからこそ「使い勝手」や「耐久性」はとっても重要です。
チェックすべきポイントは以下の通り。
- 木の厚み:薄すぎるとすぐに割れる
- 組み立ての精度:蓋や段がガタつかないか
- 持ち手の有無:熱くなりやすいので地味に重要
- 手入れのしやすさ:水はけや乾きやすさも◎
長く愛用したいなら、しっかりした作りの国産品や、信頼のブランド品がおすすめ。
特に「吉冨士工芸」などの国内メーカーは細部までこだわって作られている印象です。
私の愛用せいろも、4年目に突入してますが、まだまだ現役!
せいろを使うならこれ!活用レシピと便利テクニック

せいろを使うならこれ!活用レシピと便利テクニックを紹介します。
「せいろって何に使えるの?どう使ったらいいの?」と迷っている方は必見です!
定番の蒸し野菜&味噌だれで栄養たっぷり
まずおすすめしたいのが、超王道の「蒸し野菜」。
にんじん、ブロッコリー、さつまいも、きのこ類など、お好みの野菜をせいろに入れて蒸すだけ。
特にせいろで蒸すと、素材の甘みや旨みがギュッと引き立つんですよね。
調味料は「味噌+みりん+ごま」の味噌だれが相性抜群!
蒸した野菜にそのままディップして食べると、野菜嫌いの子どももパクパク食べちゃうレベル。
しかも油を使わないからヘルシーで、ビタミンやミネラルの流出も最小限。
私もこれを始めてから、サラダより蒸し野菜派になっちゃいました(笑)
肉まん・しゅうまい・餃子もプロの仕上がり
せいろの真骨頂といえば、やっぱり点心系!
市販の冷凍肉まんやしゅうまいを、レンジじゃなくてせいろで蒸すだけで、ふわっふわ&しっとりの仕上がりに大変身します。
餃子も、せいろで蒸すとモチモチの皮に包まれた具材の旨味がしっかり感じられて、まるで中華レストランの味。
もちろん手作りの点心もOK!
豚肉・ネギ・しいたけなどで簡単にしゅうまいも作れちゃいます。
「冷凍食品なのにこんなに美味しいの!?」と友人に驚かれたのが、ちょっと嬉しかったエピソードです〜
蒸しパンやプリンまで作れる万能せいろ
「えっ、せいろでプリン?」と思った方、実はせいろってスイーツも得意なんですよ。
たとえば、ホットケーキミックスと豆乳、卵を混ぜて型に入れて蒸せば、ふわもちの蒸しパンが完成!
プリンも、湯煎で作るより火の通りがやさしくて、なめらかな仕上がりに。
「ケーキ型が入る大きめサイズを選んでおいて良かった〜」と思う瞬間ですね。
おやつ作りも楽しくなるので、親子で一緒に楽しむのもおすすめですよ♪
実際、我が家では休日の定番になってます!
下ごしらえや作り置きにも大活躍
せいろの使い道は調理だけじゃありません。
たとえば、野菜の下茹での代わりにせいろで軽く蒸しておけば、色も栄養もキープしたまま保存可能。
作り置きのおかずも、食べる前にせいろでサッと温めれば、まるで作りたてのような仕上がりになります。
電子レンジよりもムラなく加熱できるので、食感も風味も段違い。
冷凍おにぎりやお惣菜の再加熱にもおすすめで、私はもう「レンジ=時短」じゃなくなってきました…!
使えば使うほど、せいろの底力に驚かされます。
お手入れのコツとカビ対策
せいろって木製だから、お手入れが面倒そう…と思いきや、実はそこまで難しくありません。
使用後は、すぐにぬるま湯でサッと洗って、しっかり乾かすこと。
洗剤は基本使わず、気になるときは重曹水などで優しくこすりましょう。
乾燥が甘いとカビの原因になるので、風通しの良い場所で陰干しがおすすめ。
また、使う前に5分ほど空蒸し(予熱)しておくと、木が蒸気を吸いすぎず傷みにくくなります。
収納の際には、新聞紙や通気性のある布でくるんでおくと◎
正しい手入れをしてあげれば、5年10年と使い続けられますよ〜!
初心者におすすめの調理手順まとめ
せいろを初めて使う人に向けて、基本の使い方をまとめてみました!
- 鍋に水を入れ、沸騰させる
- 蒸し板または鍋の上にせいろをセット
- 食材をクッキングシートの上に並べる
- 中火で10〜15分ほど蒸す
- 火傷に注意して取り出す
- 使用後はぬるま湯で洗ってしっかり乾かす
これだけでOKです!
「え、こんなに簡単なの?」って思うかもしれませんが、本当にシンプルなんです。
最初は緊張しますが、1回使えば感覚がつかめてハマりますよ♪
せいろを楽しむライフスタイルアイデア
せいろを取り入れると、生活そのものがちょっと豊かになります。
たとえば…
- 朝食に蒸しパンと温野菜で、やさしい1日の始まり
- 夕飯にせいろで蒸したメインと副菜を一気に仕上げる時短調理
- 休日に友達を呼んで点心パーティー♪
- 罪悪感ゼロの“ヘルシーおやつ時間”を楽しむ
毎日の「食べる時間」が、なんだか特別なものに感じられるんですよね。
せいろは単なる調理道具じゃなく、“暮らしの質”をちょっとだけ底上げしてくれるアイテムなんです。
私は、そんなライフスタイルを一緒に楽しむ人が増えてくれると嬉しいな〜って思っています!
まとめ
せいろは、ダイソーや無印良品などの実店舗から、中華街の専門店、Amazonや楽天といった通販サイトまで、さまざまな場所で購入できます。
選ぶ際には、サイズ・段数・素材に注目し、自分のライフスタイルに合ったものを選ぶのがポイントです。
初心者には鍋付きのスターターセットやレビュー評価の高い商品がおすすめで、特に竹製や杉製のものは人気があります。
また、蒸し野菜・点心・プリンなど、せいろを活用したレシピは日々の食卓を豊かにしてくれます。
せいろを取り入れることで、料理も気分もワンランクアップ。
公式サイトやレビューサイトを活用して、ぜひお気に入りのせいろを見つけてくださいね。
▼参考リンク: